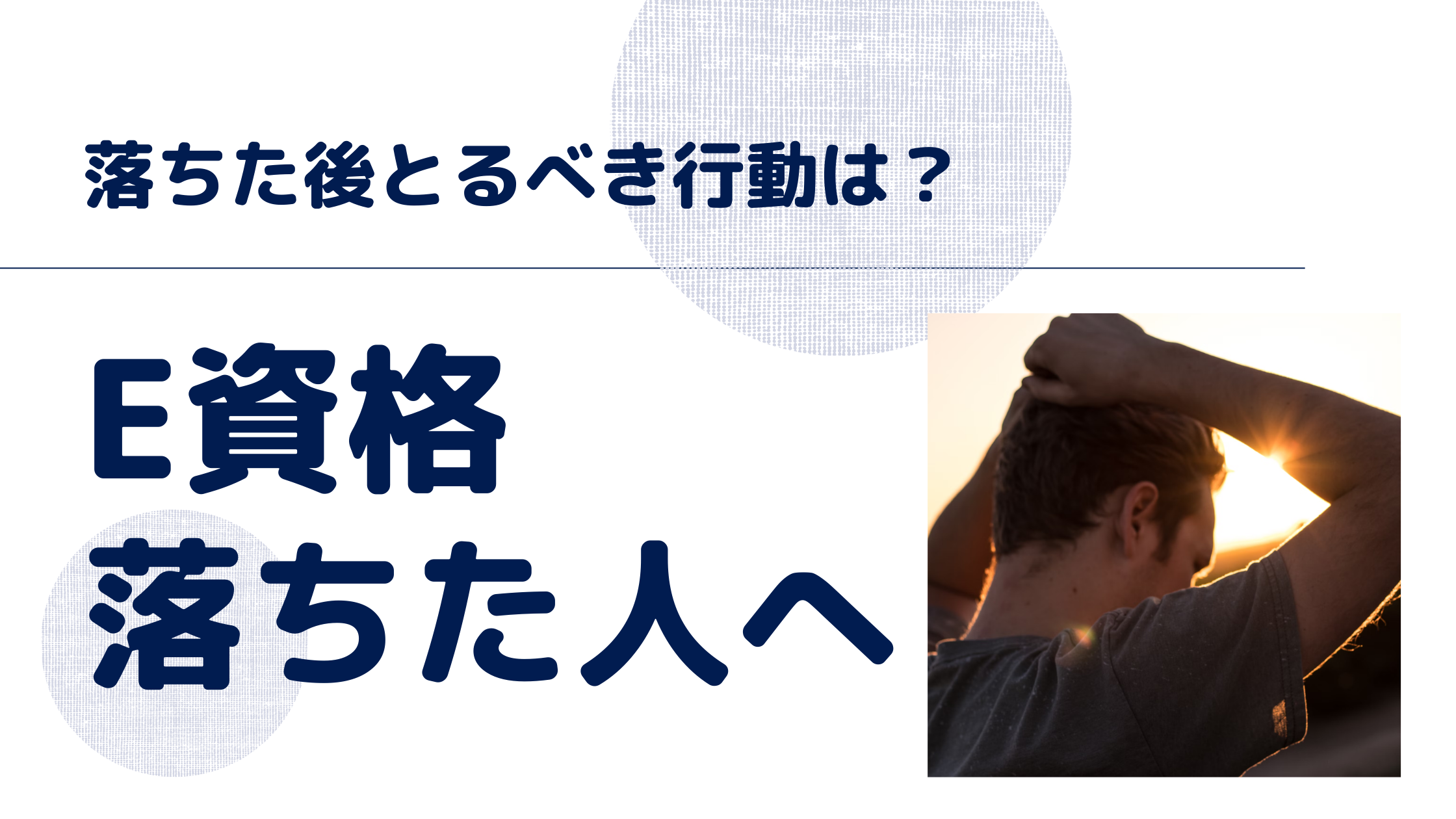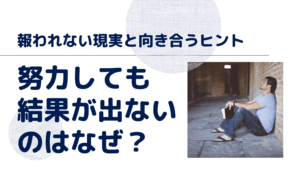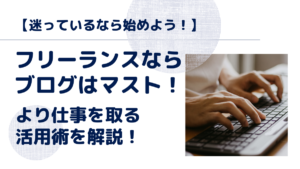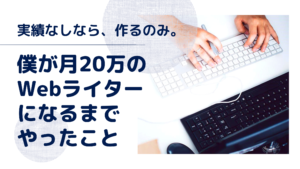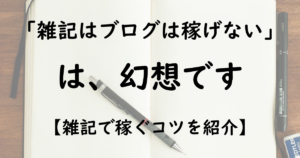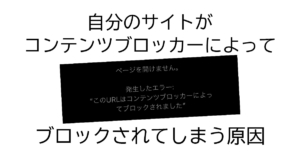悩む人
悩む人E資格落ちちゃった…。
高いお金をかけたのに悔しい。
諦めるべきかな?
でもこれまで頑張ったから受けたい気持ちもある。
けどお金が痛ましい…!
どうしたらいいだろう。
このような方へ向けた記事になります。
- E資格に落ちたあとのショックから早く立ち直れます。
- E資格に落ちたあとの正しい判断と行動が取れるようになります。
E資格に落ちた人へ


何十時間も学習してきて、安くない受講料も払って…
だからこそ落ちたと知ったときのショックや悔しさは痛いほどわかります。
ですが、ここで立ち止まるか前に進むかで、未来は大きく変わります。
E資格に落ちたことで受験料は失いましたが、決して「ムダ」ではありません。
知識も経験値も確実に蓄積されているはずなので、むしろ「落ちた」という現実をどう受け止め、どう動き出すかが次の合否を分けるポイントになります。
次章で、実際にどのくらいの人がE資格に落ちているのかを見てみましょう。
3万円も払って試験に落ちたのはあなた一人じゃないことは、ぜひ頭に入れておいてください。
E資格に落ちる人の割合


E資格に落ちる人の割合は、例年おおよそ30%、逆に例年の受かる人の割合がおおよそ70%です。
最新のデータで言うと、2025年2月の試験だと落ちた人の割合が31.74%です。
人数にすると受験者数は総計1,043名、そのうち合格者は712名、不合格者は331名となります。
「70%受かるなら簡単そう」と思うかもしれませんが、受験者の大半は理系出身者やAI関連の実務経験者。
その中での3割不合格というのは、決して軽く見ていい数字ではありません。
参考:JDLA公式サイト
文系出身や未経験の方にとっては、専門用語の壁や深層学習理論の難しさもあり、実際には想像以上にハードルが高い資格試験なのです。
次章では、その具体的な原因について見ていきましょう。
E資格に落ちた主な原因


E資格に落ちた主な原因は、シンプルですがズバリ以下が挙げられます。
- 勉強時間が圧倒的に不足していたから
- 過去問題があまり出回ってないから
それぞれ解説します。
勉強時間が圧倒的に不足していたから
E資格に落ちる大きな理由のひとつが、「勉強時間の圧倒的な不足」です。
合格率が70%以上とはいえ、受験者の多くは理系出身者であり、大学時代から数学や統計をしっかり学んできた人たち。
またこの手の人たちはAI関連の実務経験者も多く、日々の業務でディープラーニングに触れているような環境の中にいます。
そんな中で、文系や未経験の方が「過去問をちょっとやっただけ」で受かるほど甘くはありません。
E資格では、数理統計やニューラルネットワークの理論、実装技術に関する専門用語が大量に出題されます。
土台がないまま挑んでしまえば、太刀打ちできないのも当然です。
過去問題があまり出回ってないから
言い訳のようにはなると思いますが、あまり過去問が出回っていないことも、E資格に落ちる原因のひとつです。
一般的な資格試験と違い、E資格の問題はネット上での掲載が禁止されています。
そのため、実際の過去問を無料で探すことはほぼ不可能です。
唯一の手段は、対策書籍を購入することですが、当然ながら毎年出題内容や傾向は変わります。
つまり、書籍に載っている問題を暗記しても、それだけでは対応できないケースが多いというわけです。
過去問がないぶん、「試験の感覚をつかみにくい」「勉強の方向性に不安が残る」と感じる方も多く、それが結果として不合格につながってしまうこともあります。
E資格に落ちて凹んでしまう理由


E資格に落ちて凹んでしまう理由を、以下のとおり紹介します。
- 思うような結果にならなかったから
- 高い受講料を失ってしまったから
- リベンジすべきか否かの判断がつかないから
思うような結果にならなかったから
当たり前ですが「やれることはやったはずなのに、結果がついてこなかった」となるため、辛く感じます。
E資格は、事前に高額な認定プログラムを受け、数十時間におよぶ学習を積み重ねてようやく挑める試験。
だからこそ、「こんなに頑張ったのにダメだった」という挫折感はとても大きくなります。
本気で合格を目指していた人ほど、結果が出なかったことで自己否定につながりやすく、気持ちが沈んでしまうのも当然です。
高い受講料を失ってしまったから
E資格は、受験資格を得るためにまずJDLA認定プログラムの修了が必須です。
その講座費用は安くても7~10万円弱、高ければ80万円以上、加えて受験料そのものにも3万円がかかります。
なので試験に落ちてしまった場合、「お金がムダになった」と感じるのは自然です。
でも実際のところ、「ムダ」ではありません。
たとえ結果が出なかったとしても、得た知識や学習経験は確実に残るからです。
お金は失ったかもしれませんが、それは今後の業務やスキルアップに活かせる「見えない資産」として、確実に積み上がっています。
リベンジすべきか否かの判断がつかないから



E資格、もう一度受けるべきか、それともやめるべきか…
この判断がつかずに、気持ちがぐるぐるしてしまう人は多いです。
なぜなら、その判断がもう決まってれば、別に悩まないですよね。
「もうやめよう」と吹っ切れるならそれも前進だし、「絶対リベンジする」と決めていればすぐ次の行動に移せます。
でも今はその間にいるから苦しい、というわけです。
次章では、リベンジすべきか否かの見極め方法について書いていきます。
E資格に落ちた際のリベンジするか否かの見極め方法


ここでは、E資格に落ちた際のリベンジするか否かの見極め方法を紹介します。
リベンジしたほうがいい人
リベンジしたほうが良いのは、次のような人です。
- あとわずかで合格できた人
- 資格をとることでその分のリターンが得られそうな人
手応えはあったけど点数が少し足りなかった、惜しかった…という人なら、あと少しの対策で合格を狙える可能性が高いです。
また
- 社内評価
- 転職活動
- AI案件への関与
など、E資格を取得することで確実な見返りが得られる状況なら、投資した時間とお金が将来リターンとして返ってくるはずです。
目的がはっきりしていて、リベンジ後にどう活かせるかがイメージできるなら、ぜひもう一度挑戦すべきです。
諦めたほうがいい人
諦めたほうがいい人は、次のような方です。
- リベンジ成功後のリターンが見込めなさそうな人
- 損失回避志向だけで取りたがっている人
資格そのものを活かすビジョンがないまま、ただ「落ちたのが悔しい」という気持ちで再挑戦しても、結果的にE資格をあまり活かせない気がします。
それに、損失回避のための勉強は、途中でモチベーションが切れがちです。
E資格は時間も費用もかかるからこそ、「本当に必要か?」を見極めたうえで決断したほうが、後々の後悔を減らせます。
「2度目のE資格も落ちた」とならないための対策


ここでは、「2度目のE資格も落ちてしまった…」とならないための対策を、以下のとおりご紹介します。
- 手応えと結果を分析して学び直す
- できるだけ早く再受験する
手応えと結果を分析して学び直す
まずやるべきは「自分の手応え」と「結果」を冷静に分析することです。
なぜなら、実際に受けてみた感覚は、自分が一番よくわかっているはずだからです。
- 「あの問題は解けた」
- 「知識はあったけど解釈を間違えた」
みたいに惜しい内容が多かったなら、同じ方針で過去問や類題を繰り返せば合格は近いです。
逆に、
- 「まったく歯が立たなかった」
- 「問題文すら読み解けなかった」
という場合は、もう一段階レベルを下げて、基礎から学び直す必要があります。
大事なのは感情ではなく、事実と向き合って戦略を立て直すことです。
できるだけ早く再受験する
- 「もう少しで受かりそうだった」
- 「勉強の習慣がまだ身についている」
という人ほど、再受験は早めのタイミングがおすすめです。
なぜなら学んだ内容は時間が経つほど薄れてしまいますし、モチベーションもどんどん落ちていくからです。
E資格は年に2回(2月・8月)しかチャンスがないため、「次の試験まであと○ヶ月」と逆算して計画を立てやすいです。
また、一度試験を経験している分、出題形式や時間配分にも慣れており、次はより実力を出しやすくなります。
「鉄は熱いうちに打て」です。
E資格落ちた人へ向けた記事まとめ
本記事の内容をまとめます。
- E資格の合格率は約68%、つまり約3割が落ちている
- 理系出身・実務経験者が多く、文系未経験には難易度が高め
- 落ちる主な原因は勉強時間不足と、過去問が出回っていないこと
- 落ちた後の判断は「資格をどう活かすか」がカギ
- リベンジするなら早めに再受験し、戦略的に学び直すべき
- 失敗はムダではなく、知識と経験として必ず残る
E資格に落ちてしまったショック、悔しさ、そして金銭的ダメージ、どれも痛いほどわかります。
ただ、落ちたのはあなただけではなく、毎回3割ほどの受験者が涙をのんでいます。
大事なのは、「それでもこの資格を取る意味が自分にあるのかどうか」を見極めることです。
今は辛いかも知れませんが、なるべく早く立ち直って、リベンジするか否かを決断し、淡々と動いていきましょう。


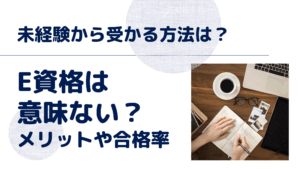
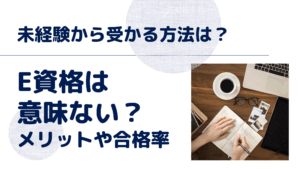


1992年生まれ|2020年10月フリーランスとして独立|Web制作、SEOライティングを軸に活動中|接客→生産管理→システム開発会社→現在|モリブログ運営。Web制作、フリーランスジャンルを中心に更新中。PV数は年間14万人以上||温泉、旅行、甘いものが好き。