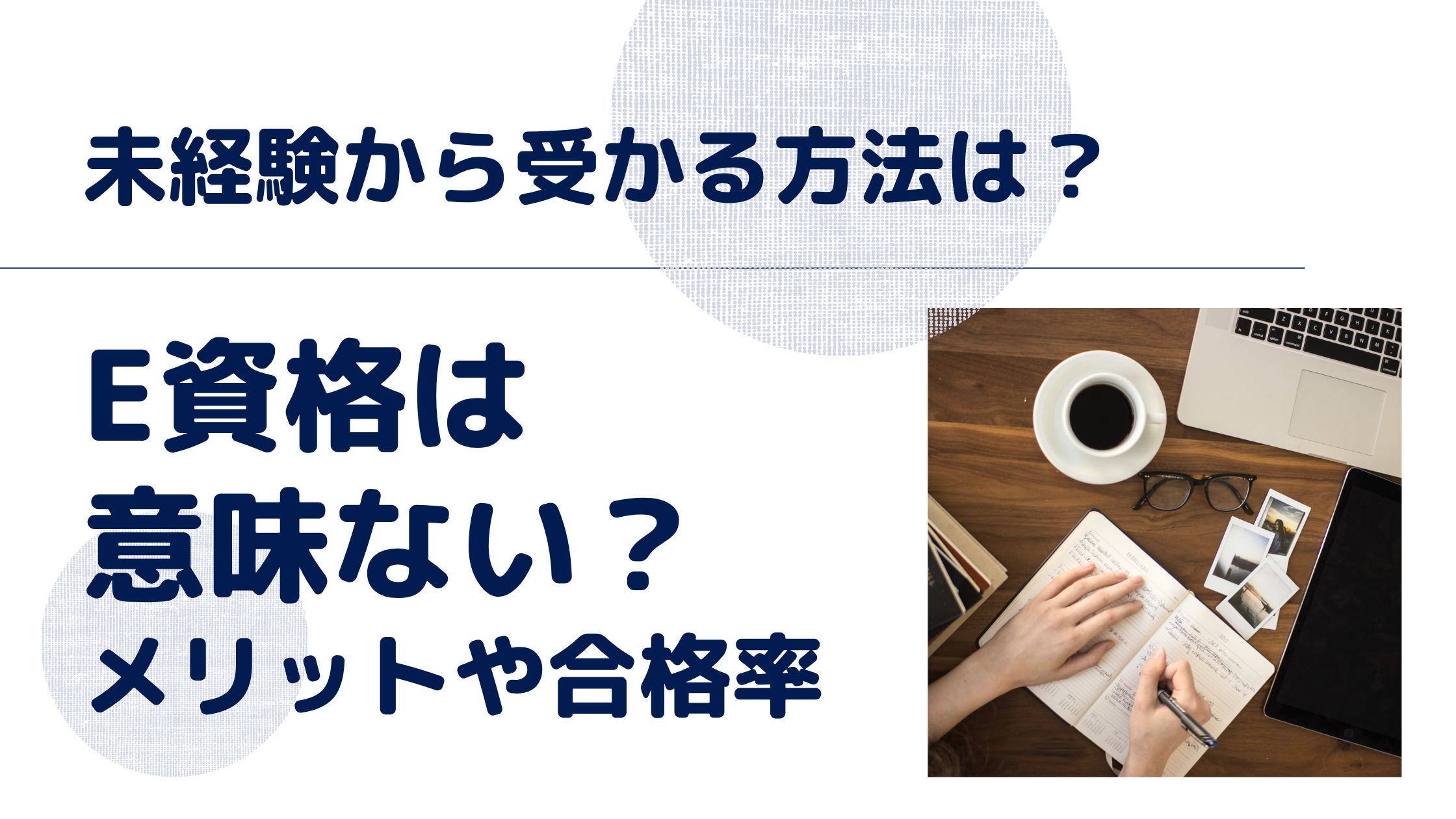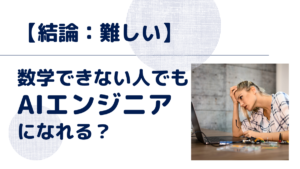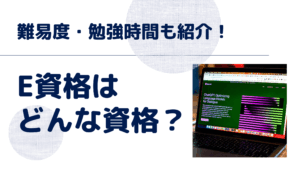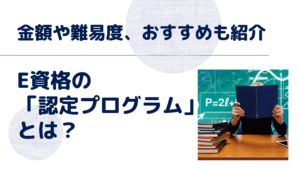悩む人
悩む人これから来るAIの波のためにもE資格を取りたい。
でもいろんな場所で「E資格は意味ない」って言われてる。
実際のところどうなんだろう?
このような方へ向けた記事になります。
- E資格に挑戦するモチベーションが上がります。
- 完全未経験の方がE資格に受かる現実的な勉強法がわかります。
「E資格は意味ない」は嘘です【その理由】


結論、E資格は意味のある資格です。
後にも紹介するのですが、理由は
- 今後くるAIの波に乗りやすくなるから
- AI人材が不足する中で希少価値が上がるから
- 使い道もたくさんあるから
です。
また「理系向けで難関な資格を取得した」こと自体を評価してもらえるケースも多いので、E資格はすこし値は張りますが損することはないでしょう。
ではなぜE資格が意味ないと言われる?


結論としてE資格は意味があると言いましたが、「意味ない」と言われるのにはやはり理由があるもの。
その理由は主に以下です。
- 低い合格率の割にはメリットが少ないから
- 結局求められるのは資格じゃなく「経験」だから
それぞれ詳しく解説していきます。
低い合格率の割にはメリットが少ないから
理由1つ目は、合格に必要な労力に対し、メリットはそれほど大きくないからです。
E資格の合格率は例年約65~75%と高く、数字だけ見ると「簡単じゃん」と感じます。
参考:JDLA公式サイト
しかしE資格の受験者は理系大学出身者やAI業界経験者が多く、その方たちのおかげで合格率が底上げされているのです。
過去問題を見ると、聞き慣れない用語や記号ばかりが羅列しているので、未経験者や文系出身者はひと目で「あ、これは無理なやつだ」と察すると思います。



これだったら別の資格で、もうちょいカンタンで役立つやつあるよね…。
となるので、「意味がない」と言われてしまうわけです。
結局求められるのは資格じゃなく「経験」だから
エンジニア求人と同様ですが、就職にせよ業務委託にせよ、企業が求めているのは資格じゃなくて「経験」です。
一般的には必須条件として経験、歓迎される条件として資格が記載されることが多くなっています。
つまるところ、資格で求められる知識と、仕事で求められる知識は大きく異なるということがわかります。
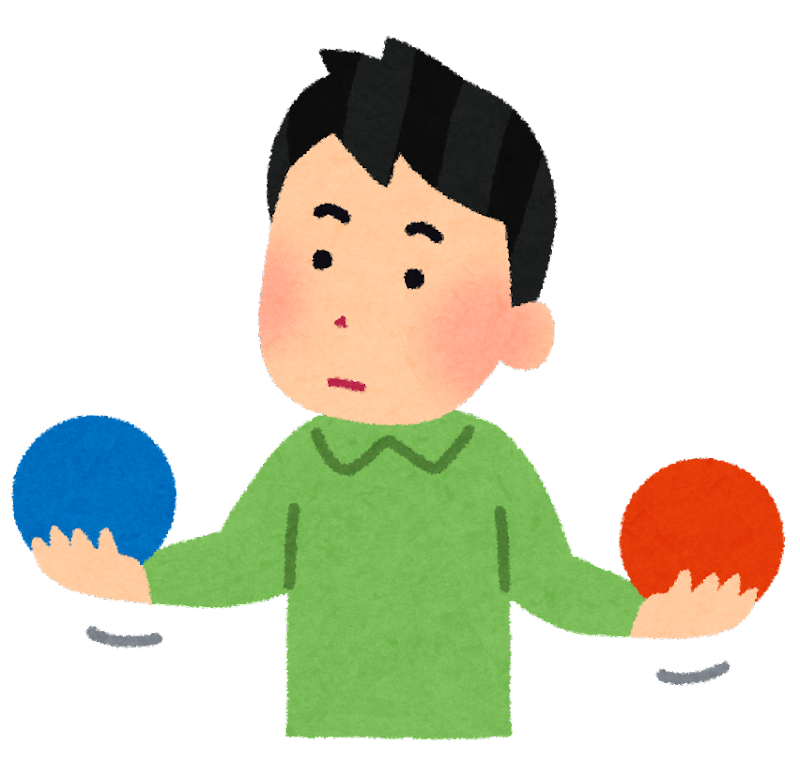
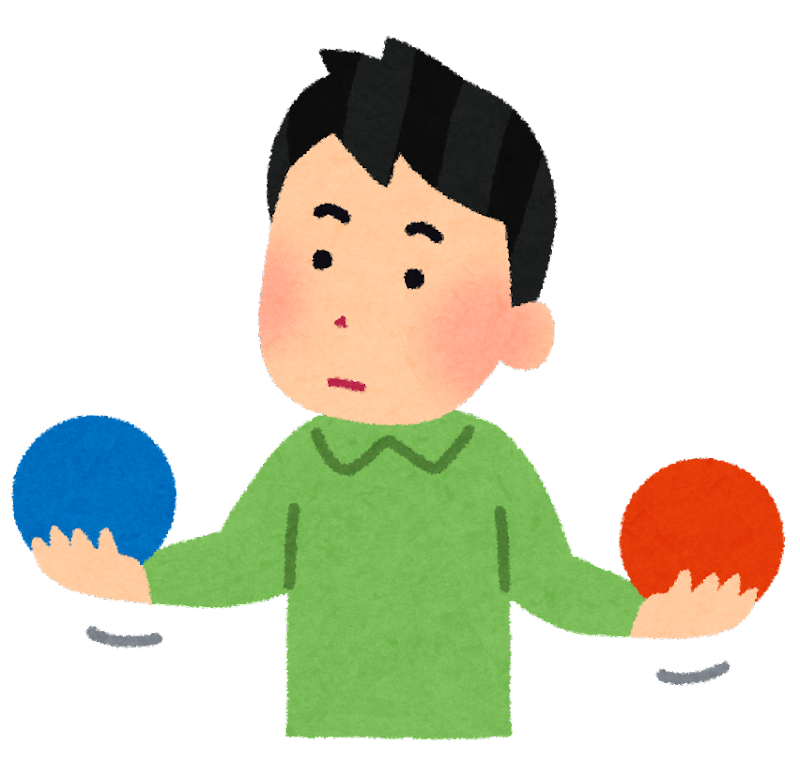
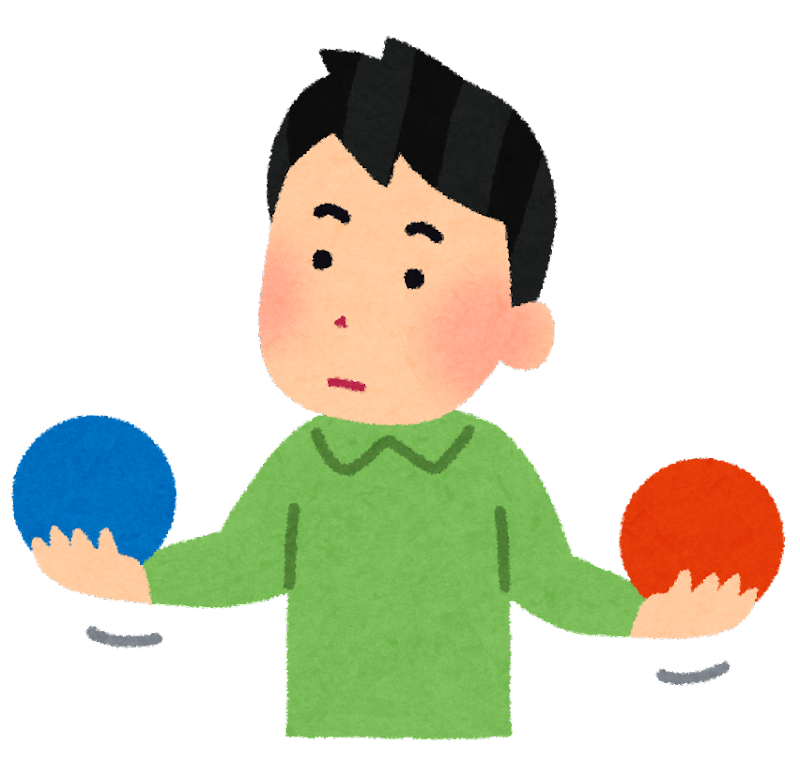
多くの時間をかけて資格を取りに行くより、経験を0→1にすることにコミットしたほうが再現性が高いよね
こう考える方が多いのも納得ですよね。
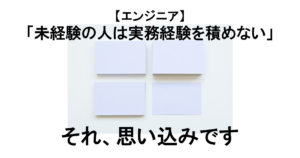
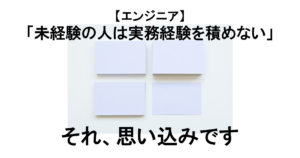
E資格を取得するメリット
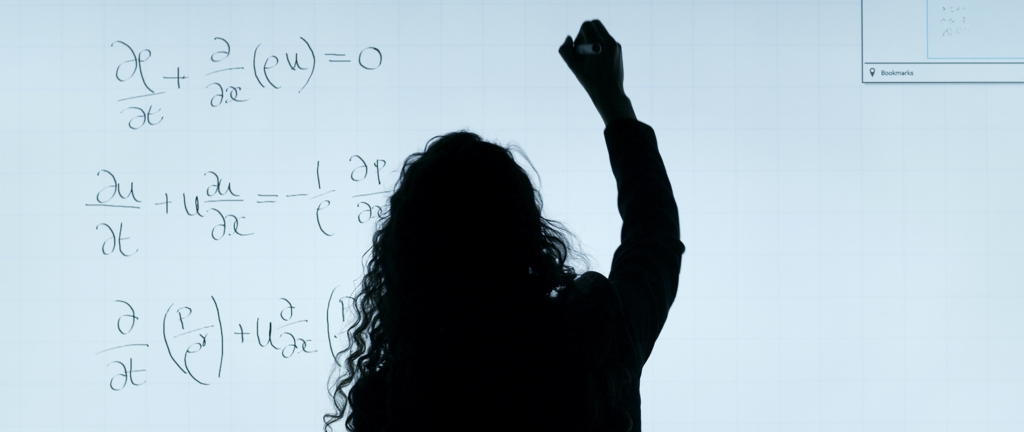
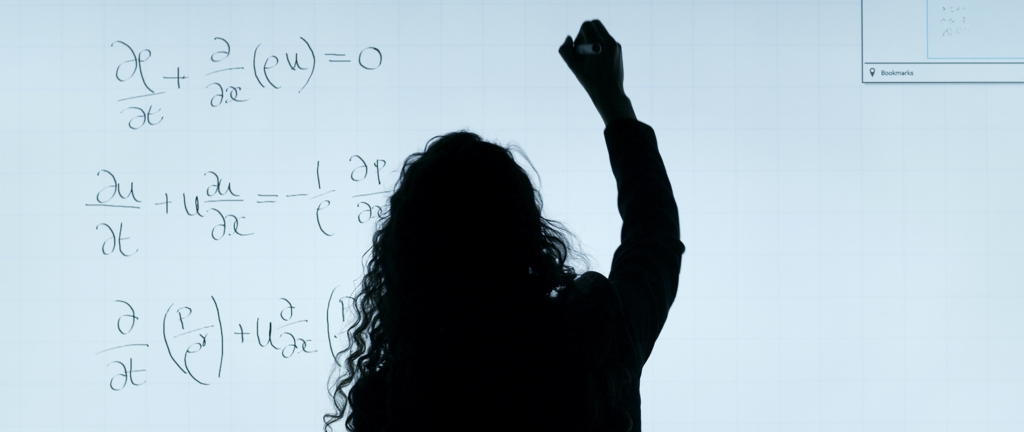
E資格は意味ないと言われる理由を解説しましたが、それでもE資格は大いに意味のある資格といえます。
ここからは、E資格をとるメリットを紹介しますので、挑戦のためのモチベーションにつなげてください。
今後くるAIの波に乗りやすくなる
すでに到達しているAIの波ですが、今後はもっと高度で人々を驚かせる技術が生まれ、波はさらに大きくなるはずです。
この波に乗りやすくなるのが、まず大きなメリットになります。
E資格をもっていると、AI関連の情報発信を行う際などに、存分に権威性を発揮できるからです。
それだけでなく試験範囲が実務寄りであるため、AI関連の就職にもしやすくなります。
前述で「資格<経験」と説明していますが、ド素人から経験0→1にするための方法として、資格をとって意欲とポテンシャルをアピールするというのは非常に有効です。
AI人材が不足する中で希少価値が上がる
AI市場はさらに加速し、もっと大きくなるのは間違いないです。
その波の中で確実に考えられる課題は、「AI人材の不足」です。
なぜかというと、現代ではただでさえ「IT人材」がこれだけ不足している中で、「AI人材」が不足しないわけないからです。
その波の中で、「AIを触れる人材である」というのを証明できるのは、希少価値が大きく上がり、選択肢も大きく広がります。
使い道がたくさんある
E資格で学んだ知識はAIエンジニアとしてはもちろん、データサイエンスやマーケティングなどさまざまな分野で使えます。
AIエンジニアとしての就職だけでなく、その汎用性の高さもメリットといえます。
どんな使い道があるかは、次章で紹介します。
E資格の使い道(AIエンジニア以外)
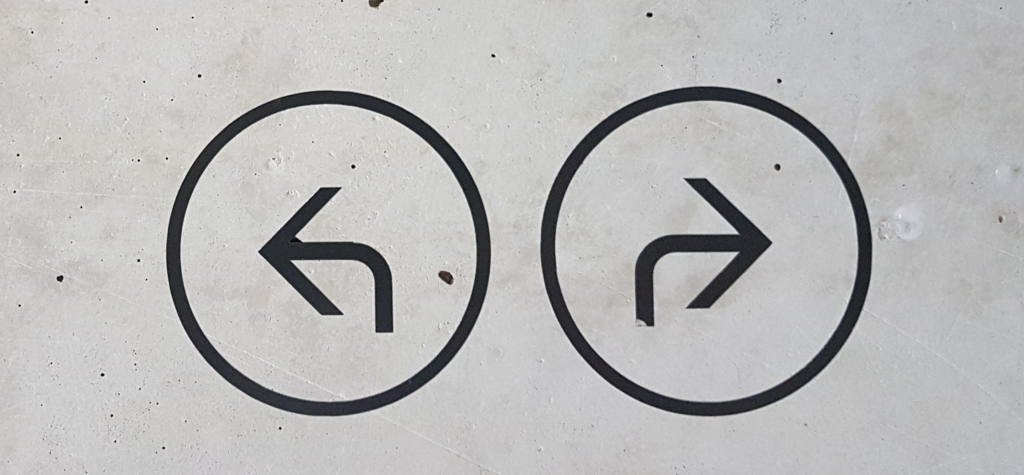
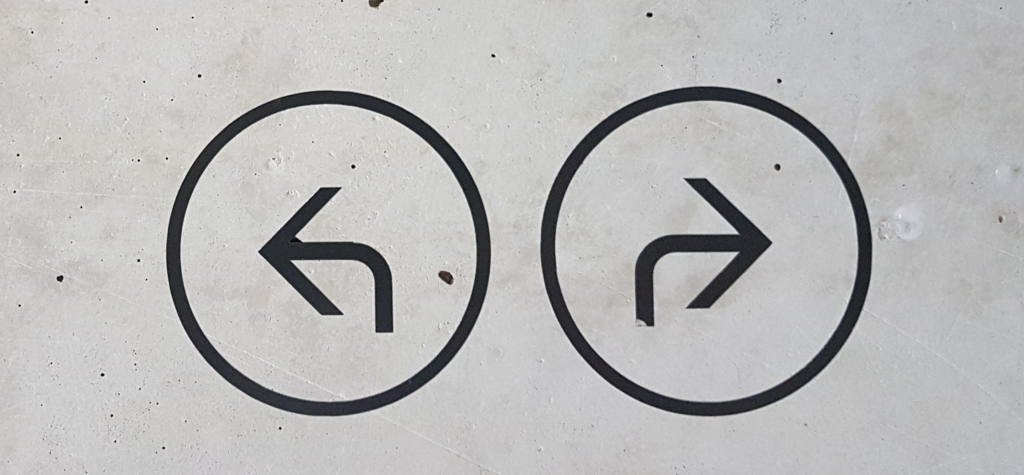
E資格の使い道(AIエンジニア以外)を、以下のとおりご紹介します。
- データサイエンティスト
- Webマーケター
- プロジェクトマネージャー
データサイエンティスト
E資格の知識は、データサイエンティストとしても役立ちます。
E資格によってディープラーニングの仕組みやモデル選定の考え方が理解できていると、より本質的なデータ分析ができるようになるからです。
数値の裏にある意味を見抜き、さらにAIを活用した高度な予測や意思決定支援ができるようになるので、分析業務の質が一段と上がるでしょう。
Webマーケター
Webマーケターも、E資格の知識を活かせる場面が意外と多いです。
たとえば顧客行動の予測モデルを自分で理解できれば、AIツールを「なんとなく使う」ではなく「意図して使いこなす」ことができます。
機械学習を前提にした広告運用やコンテンツ最適化においても、提案力・説得力が増すのは間違いないでしょう。
プロジェクトマネージャー
PMがE資格の知識を持っていると、AI案件のハンドリングに強くなります。
技術者と対等に会話ができるようになるため、要件定義やリスク判断の精度が上がりますし、チームとの連携もスムーズになるでしょう。
ITコンサルタント
ITコンサルタントがE資格を持っていると、AIを絡めた提案の説得力がぐっと増します。
単に流行りの技術を紹介するだけでなく、「この仕組みだからこの課題に効く」と、技術的な裏付けをもって話せるのはかなり強いです。
実装フェーズで技術者とズレずに話せるのもメリットですし、顧客からの信頼も厚くなります。
知識ゼロの未経験からE資格に受かる方法


ここまでの内容を読んで、なおさら



まったくの未経験だけど、E資格をとりたい!
と思った方も多いと思います。
この章では、「知識ゼロの未経験から」E資格に受かる方法を紹介します。
過去問をコツコツ解いて覚える
当たり前すぎて申し訳ないのですが、結局これがもっとも再現性が高い方法になります。
とにかく過去問題集を解きまくって、出題の内容や傾向を掴むことです。
E資格に限りませんが、勉強はアウトプット8割、インプット2割で行うのがベストだからです。
最初は正解率2割にも満たない状況が続くので絶望するしかありません。
ですが、とにかく1冊を丸暗記でもいいから解くことを繰り返していくと、だんだんと知識がついてきます。
ここでふるいにかけられ、粘る人と離脱する人が分かれるんだと思います。
講座やセミナーで学習を加速させる
「受かる方法」というより、E資格受験には「JDLA認定プログラムの受講」が必須条件となっています。
JDLA認定プログラムは実質セミナーのようなものなので、
- どうしても独学が苦手
- 勉強計画や自己管理が苦手
- 学習時間を短縮させたい
という方にもぴったりです。
ただJDLA認定プログラムはどれも料金がやたらと高いので、月額3,300円から試せるStudy-AI運営のラビットチャレンジあたりを試してみるのがいいでしょう。
まずはサクッと安く講座を受講し、必須条件をクリアすることです。
また、JDLA認定プログラム外ではありますが、AIコースのあるプログラミングスクールで学ぶのもひとつの方法です。
「E資格は意味ない」に関連するQ&A
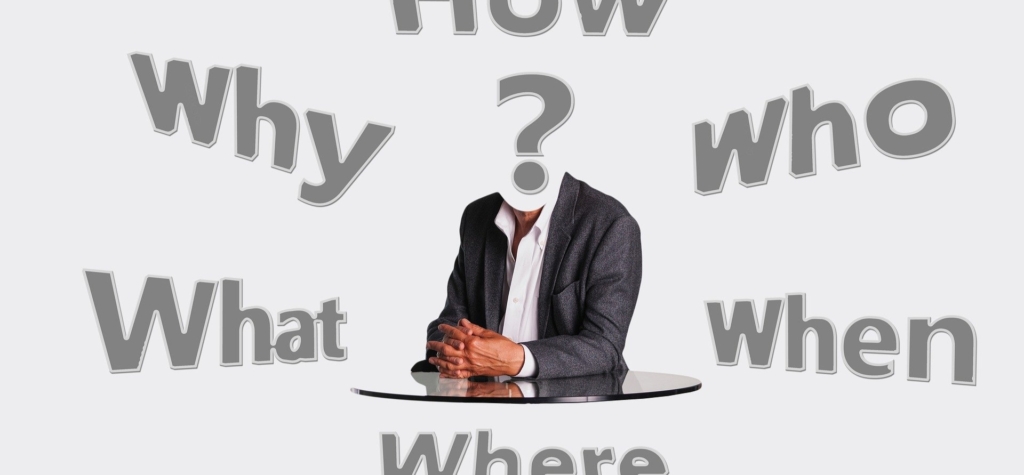
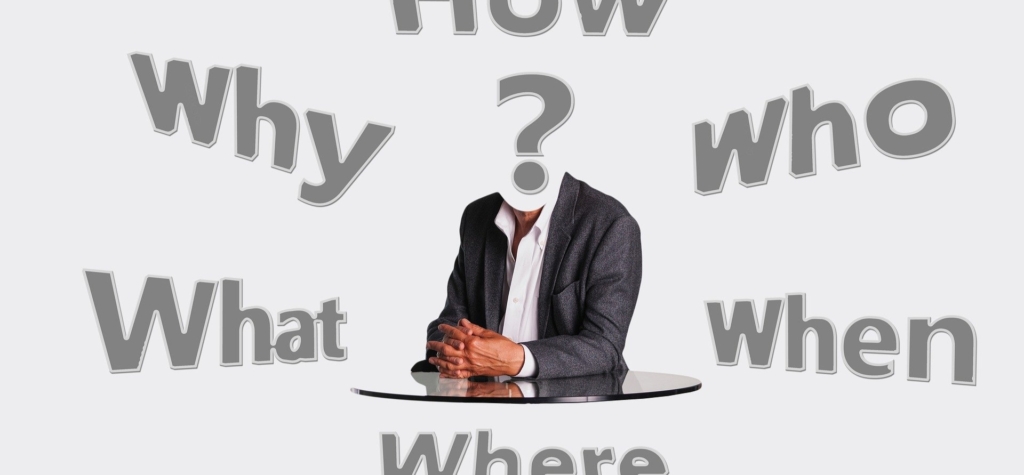
ここでは、「E資格は意味ない」と言われることに関連するQ&Aを紹介します。
- E資格取得後の年収相場はどれくらい?
-
あくまで概算にはなりますが、年収582.3万円くらいは狙えるでしょう。
厚生労働省が運営するサイト「job tag」によると、一般的なAIエンジニアの平均年収は558.3万円です。
これにE資格による資格手当(月々20,000円と仮定)を加えると、582.3万円になります。
ただ企業によっては、報奨金として2~3万円を一度支給するだけで終わったり、報奨金がないケースもあるので一概にはいえません。
- E資格の難易度はどれくらい?
-
E資格の合格率は例年約65~75%なので、一見簡単そうに感じます。
参考:JDLA公式サイト
しかしE資格の受験者は理系大学出身者やAI業界経験者が多く、その方たちのおかげで合格率が底上げされているのが現状です。
未経験者や文系出身者が見ると、まったく見慣れない単語や記号に圧倒される、難関な資格と言って過言ではありません。
- E資格にはどれくらいの勉強時間が必要?
-
こちらもペースや集中力によるので一概にいえませんが、僕の体感だと未経験の場合、少なくとも150~200時間は必要です。
これは約5~6時間程度の学習を1ヶ月休みなしで続けた場合に実現できる数字です。
働きながらこれを続けるとなれば2~3ヶ月はかかるかもしれません。
- 未経験ならG検定とE資格どちらをとるべき?
-
G検定でして、理由はE資格よりはカンタンだからです。
未経験ならまずはG検定で基礎を作り、それに受かったらスキルアップとしてE資格に挑戦するほうが挫折率は減らせるでしょう。
初っ端からE資格に挑戦すると、挫折の可能性が高くなります。
「E資格は意味ない」に関するまとめ
今回の記事をまとめます。
- E資格は意味がある
- ただし低い合格率と実用性の観点で敬遠されがち
- E資格は今後来るAIの波に乗りやすくなるほか、人材価値向上など汎用性の高さもメリット
- マーケターやコンサルタント、PMといった使い道もある
- 完全未経験から合格を狙うなら、過去問コツコツorセミナー
E資格は難しさと実用性の観点で敬遠されがちですが、今後のAI市場の拡大や波を考えるとチャレンジする価値は大いにあります。
ましてやAI業界やエンジニアは経験が求められるので、未経験であれば資格をとって意欲やポテンシャルをアピールするのが現実的な手段になってきます。
「意味ない」という情報は飛び込んできますが、奥せず挑戦することが大切です。


1992年生まれ|2020年10月フリーランスとして独立|Web制作、SEOライティングを軸に活動中|接客→生産管理→システム開発会社→現在|モリブログ運営。Web制作、フリーランスジャンルを中心に更新中。PV数は年間14万人以上||温泉、旅行、甘いものが好き。