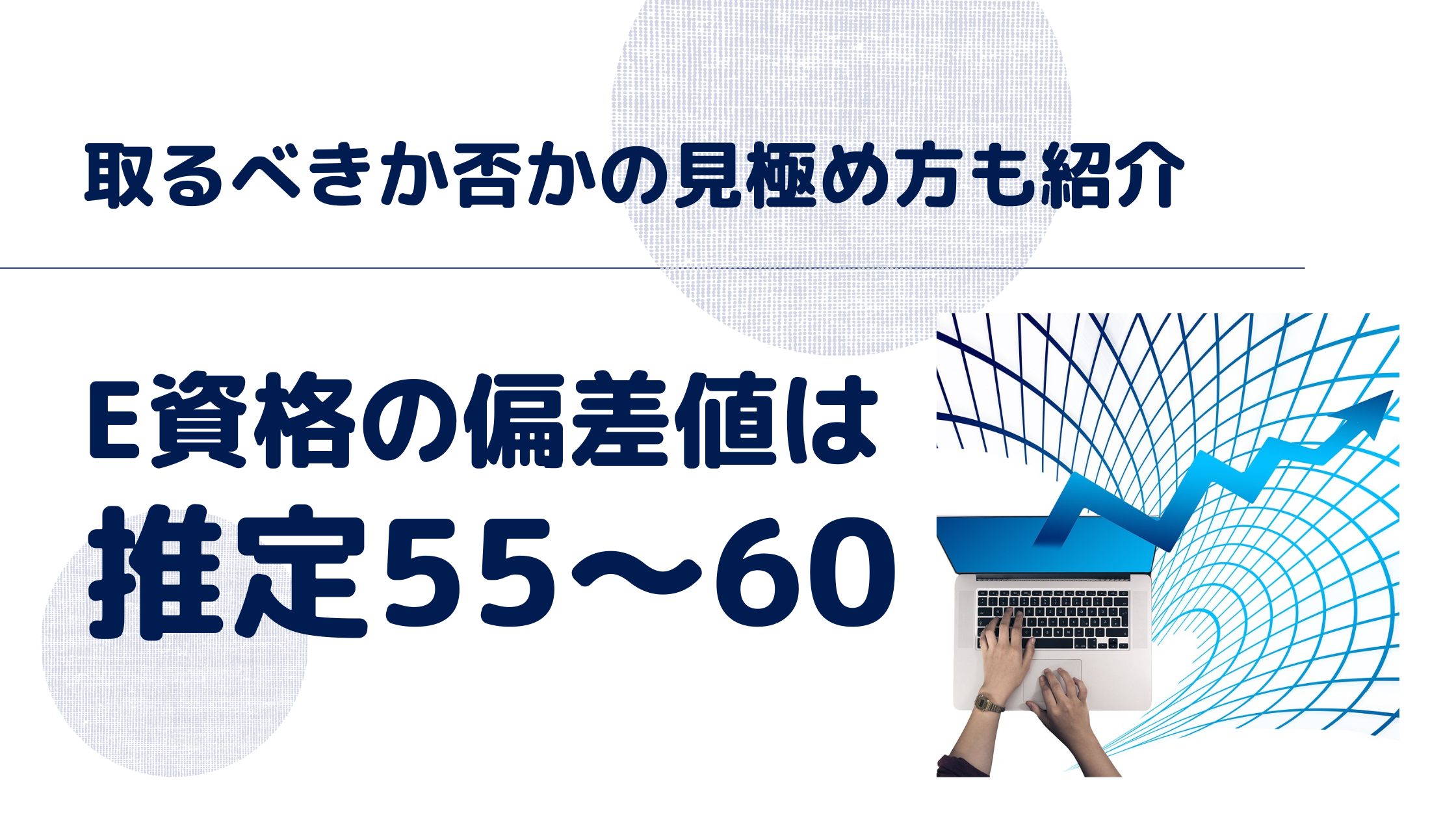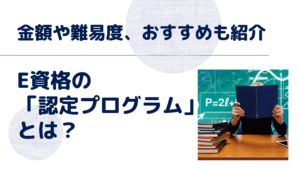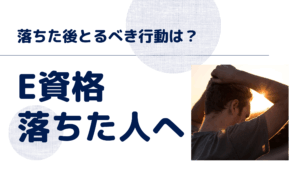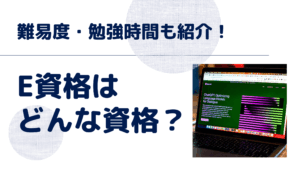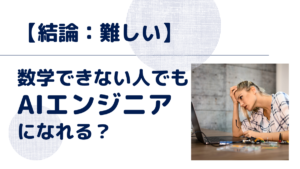悩む人
悩む人E資格って偏差値どのくらいの人が受ける資格なの?
合格率だけ見ると高いみたいだけど、自分は挑戦すべきなのかな…?
今回はこのような方に向け、E資格の偏差値および合格率、そして取るべきか否かの見極めについて書いていきます。
- 「E資格に挑戦するべきか、やめとくべきか」の決断がスムーズになります。
- 偏差値や難易度の情報に振り回されず、挑戦することへのハードルを下げられます。
- 「挑戦しない」という選択をしたときの、不安や後悔が軽減されます。
そもそもE資格とは?


E資格は、「一般社団法人日本ディープラーニング協会」が運営する民間資格です。
かんたんに言うと、AIエンジニアとしての知識をアピールできる内容となっています。
資格の概評を一覧にまとめたものが以下です。
| 資格名称 | E資格(JDLA Deep Learning for ENGINEER) |
| 主な出題内容 | 機械学習 深層学習の基礎理論(ニューラルネットワーク・CNN・RNN・強化学習など) 数理統計 Pythonプログラミング 倫理・法律 など |
| 受験条件 | JDLA認定プログラムを修了していること (修了日が試験日の2年以内である必要あり) |
| 合格率 | 約70%前後 (回によって変動。直近の2024年試験では68.5%程度) |
| 受験形式 | CBT(コンピューター上で受験する形式) 全国の指定会場にて受験 |
| 費用 | 一般:33,000円(税込) 学生:22,000円(税込) 会員企業所属者:27,500円(税込) |
E資格の難易度を偏差値にすると「55~60」くらい


すでにタイトルにありますが、E資格の難易度を偏差値にすると、あくまで推定ですが「55~60」くらいと考えるのが妥当です。
E資格の合格率は約70%なので、数字だけ見ればカンタンに見えますが、これは「事前にJDLA認定プログラムを受講した人だけが受けられる」という前提つきの数字です。
母集団がすでに絞られていて、未経験者・不合格になりやすい層が一切含まれていないため、単純な合格率では判断できないのが現状です。
ですがE資格は、受験者のじつに7割強が理工学系出身者ということがわかっています。
「理系出身が半数以上」「Pythonや深層学習の知識が前提」である点からも、比較対象である基本情報技術者(偏差値49)よりは明らかに難易度が高いと考えられます。
ただ、同じく比較対象の応用情報技術者(偏差値65)よりは、知識・実装スキルが限定的です。
出題範囲がAIやディープラーニングに片寄ってて、広範なIT知識を問う応用情報よりは範囲が狭いとなれば、総合的難易度はやや低いといえます。
なので、E資格の難易度を偏差値にすると、推定ですが55~60(平均よりやや上〜上位)あたりになります。
参考:資格の取り方
参考:JDLA公式サイト
E資格の難易度・合格率【約70%】


すでに上記でも触れていますが、E資格の合格率は約70%です。
運営元のJDLA公式サイトから、過去の合格率を抜粋したものが以下です。
| 開催回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 342 | 337 | 234 | 69.44% |
| 2019 #1 | 396 | 387 | 245 | 63.31% |
| 2019 #2 | 718 | 696 | 472 | 67.82% |
| 2020 #1 | 1,076 | 1,042 | 709 | 68.04% |
| 2021 #1 | 1,723 | 1,688 | 1,324 | 78.44% |
| 2021 #2 | 1,193 | 1,170 | 872 | 74.53% |
| 2022 #1 | 1,357 | 1,327 | 982 | 74.00% |
| 2022 #2 | 917 | 897 | 644 | 71.79% |
| 2023 #1 | 1,131 | 1,112 | 807 | 72.57% |
| 2023 #2 | 1,089 | 1,065 | 729 | 68.45% |
| 2024 #1 | 1,215 | 1,194 | 867 | 72.61% |
| 2024 #2 | 930 | 906 | 600 | 66.23% |
| 2025 #1 | 1,077 | 1,043 | 712 | 68.26% |
参考:JDLA公式サイト
上記の合格率をすべて平均すると、70.4%となります。
【結論】E資格は難しいです。未経験から合格する方法は?


結局、難しいかどうかでいうと、E資格は難しいです。
深層学習の数式や確率統計、CNN・RNN などのネットワーク設計に加え、PyTorch/TensorFlowでのコード読解やハイパーパラメータ調整など、文系出身者から挑戦するには敷居が高いです。
またE資格は、受験者の多くが情報・数学系の学歴・経歴をもっていたり、日常業務で AI を扱っている方々が多い傾向にあります。
合格率が高めに見えますが、こうした有識者が大半を占める背景もあって、平均的なエンジニアにとっては難度が高いのが実情です。
未経験から合格する方法
文系出身、完全な未経験から合格する方法としては、過去問題をひたすら解いてコツコツと問題に慣れていくのがもっとも現実的です。
また現代では、E資格対策講座として、ラビットチャレンジなどをはじめとするさまざまなITセミナーや講座があります。
独学がどうしても苦手な方は、それに投資してみるのもひとつの選択肢でしょう。
勉強法については、以下の記事でも紹介しています。
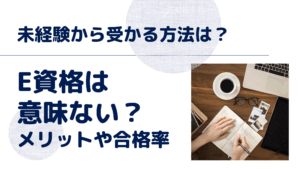
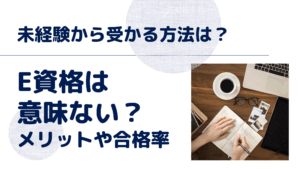
とはいえ、偏差値や合格率はあまり当てにならない


ここまで紹介していうのもですが、正直、偏差値や合格率はそれほど当てになりません。
前述でも出てきた「基本情報技術者試験」や「応用情報技術者試験」にも、おおよその偏差値水準は設定されていますが、あくまで概算であって根拠はありません。
偏差値というのは、受験者の学力レベルを統一しなければ正しく比較できないからです。
それに実際、E資格は理系出身者や実務経験者が多いとはいえ、文系や未経験からの合格者も一定数いるのも事実です。
E資格は出題範囲が明確にあり、事前に認定プログラムでしっかりと対策することが可能です。
偏差値に惑わされず、「自分のやる気次第で十分合格が狙える試験だ」と前向きに捉えるほうが有意義です。
なので偏差値はとくに気にせず、挑戦してみるのがいいと思います。
「E資格は挑戦するに値するか否か」の見極め方


偏差値を気にして本記事にたどり着いたということは、



せっかく受けるなら失敗したくない。
偏差値的に無理そうならやめておきたい…。
と心配する方が多いと思います。
この章では、E資格に挑戦したほうがいい人とそうでない人をそれぞれ紹介します。
挑戦したほうがいい人
- E資格が本業や転職の武器になる人
- もしくはゆくゆく、そのビジョンが明確に描けている人
は、挑戦したほうがいいです。
これに該当するなら、高い受験料と膨大な学習時間をリターンへ換算しやすいからです。
- 「社内でAI案件が控えている」
- 「採用要項に”E資格保有者優遇”と明記する企業へ転職したい」
など合格後の使い道が直結しているならぜひ挑戦すべきでしょう。
挑戦しないほうがいい人
- E資格を活かすビジョンが不明確な人
- とりあえずAIに強くなりたい人
- これからの流行に乗り遅れたくない人
といった漠然とした動機しかない人は、E資格への挑戦はやめたほうがいいと思います。
時間や金銭面でのコストが回収できず、リターンが少なくなってしまう可能性が高いからです。
AIおよびAIエンジニアの知識を勉強したいなら、E資格をとるよりもネットの情報などで無料で勉強したり、独学が苦手ならAIスクールなどを活用するほうが有意義です。
E資格の難易度と偏差値についてまとめ
ここまでの内容をまとめます。
- E資格の偏差値は推定55〜60、基本情報より難しく応用情報より易しい
- 合格率は約70%だが、母集団が絞られているため難易度が低くはない
- 理系出身・実務経験者が多いが、文系・未経験からの合格者もいる
- E資格は出題範囲が明確で、対策しやすい
- 偏差値や合格率に惑わされず、ビジョンがあるなら挑戦すべき
- 資格を活かすビジョンが曖昧なら、無理に受けなくても良し
E資格の偏差値は推定55〜60で、受験者の多くが理系出身とはいえ、文系や未経験から合格した人もいます。
合格率は高めに見えますが、事前に認定講座を修了した層が対象なので、数字ほど簡単ではありません。
ただ、出題範囲が明確で学習ルートも整備されているので、対策次第で十分合格可能です。
偏差値で二の足を踏むよりも、自分にとって「合格がどんな意味を持つか」を思考して決断しましょう。


1992年生まれ|2020年10月フリーランスとして独立|Web制作、SEOライティングを軸に活動中|接客→生産管理→システム開発会社→現在|モリブログ運営。Web制作、フリーランスジャンルを中心に更新中。PV数は年間14万人以上||温泉、旅行、甘いものが好き。